今日は、伝統的なヨガの朝の過ごし方に関心のある方に向けて、一部ご紹介しています。
〈アーユルヴェーダの白湯〉
疲労回復や代謝アップ、内臓を元気に、消化促進、デトックス、
飲み方によって頭痛の改善やセルライトの改善などにも役立てられています。
〈はじめに〉
数千年前から伝承されるインドの伝統医学「アーユルヴェーダ」では、5元素と呼ばれる空・風・火・水・地があるとされます。
また、アーユルヴェーダのトリドーシャ理論では、ヴァータ・ピッタ・カパの3つのドーシャ(トリドーシャ)があり、
ヴァータを構成する要素は「風」と「空」
ピッタを構成する要素は「火」と「水」
カパを構成する要素は「水」と「地」
となります。
〈アーユルヴェーダの白湯について〉
よく沸かすことで、水・火・風・地・空の5つの要素が調和し、体内にとり込むことで、ヴァータ・ピッタ・カパの3つのエネルギーのバランスを整えることができると考えられています。
【アーユルヴェーダの白湯の作り方と五元素】
〈きれいな水(「水」の要素)〉
水は、浄水器や浄水ポット等で濾過したもので作りましょう。
(白湯づくりには、ペットボトルのお水よりも水道水を濾過したものの方がおすすめです。)
〈やかんや鍋(「地」の要素)〉
やかんの材質はアルミ以外の、「地」の要素でできたものをよく選びましょう。
銅もおすすめで、鉄や土鍋など、ご自身に合った材質を選びましょう。
ステンレス製でも大丈夫です。
〈「火」の要素〉
火を使ってお湯を沸かします。
最初は強火にかけます。
アーユルヴェーダの白湯づくりでは、できるだけ、電気ポットやIHではなく、ガス火などの方が良いとされています。
〈「風」の要素〉
部屋は清潔な状態で。[→風]
外が静かな状態であれば、窓を開けて作ると良いでしょう。
空気が循環するようにします。
沸騰してから、蓋をあけてふつふつと泡が立つくらいの弱火で15〜20分ほど火にかけます。
(10〜15分でも、その日に無理なくできることを行います。)
蓋をあけるのも「風」要素です。
〈空の要素〉
朝起きてすぐ、穏やかな心の状態で、[→空(くう)の要素]
白湯を沸かします。
雑念のなく、思考の忙しく働いていない状態が大切です。
ヨガを練習している方は、一度でも、日の出の96分前に起きて浄化法から始める静かな時間を経験してみましょう。
ブラフマムフルタの時間帯(日の出の96分前〜48分前)に目覚め、クリヤや瞑想から始まる生活を行うと、忙しい日常では気付けない感覚に気付けます。
小鳥が鳴き始めるよりも早く、車もほとんど通らない時間帯に窓を開けると
普段は生活音に隠れている、日中には聞こえない自然の音を聴くことが出来ます。
心地よく、
大きな自然であったり
超越的なものと共に生きているという感覚を、
練習しようとしなくても
この時間には自然に感じることが出来、
幸福感が感じられやすいです。
瞑想も、呼吸が深まり意識的なクンバカ、無意識のクンバカ共に、想像以上の深まりがより現れやすい時間帯です。
時間帯による練習の深まりの違いも、ぜひ一度味わって頂けると嬉しいです✨
さて、一般のアーユルヴェーダの白湯づくりで伝えられることの少ない「空」の要素について、
『穏やかな心の状態』が大切です。
忙しい人が毎日ブラフマムフルタの時間に起きるのではなく、自然と同調するような感覚を経験し、いつでも思い出せることが大切です。
〈効果について〉
脂肪燃焼効果はなく、
痩せる効果はありませんが、飲み方によって疲労回復、セルライト改善、頭痛改善や、様々な不調改善に役立つことが伝えられています。
内臓を元気にすることによって消化促進効果もありますし、心を落ち着かせることによって過剰な食欲は抑える作用もあります。
飲み方のコツについては、
体調別の飲み方を生徒さまにお伝えしています。
アビヤンガ(アーユルヴェーダマッサージ)を学び、
https://clarayoga.net/archives/7649
↑コース一覧
https://clarayoga.net/archives/8036
↑アーユルヴェーダ講座について
#アーユルヴェーダライフ
#アーユルヴェーダのある暮らし




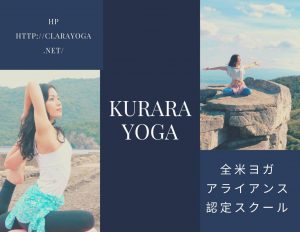




コメントを残す